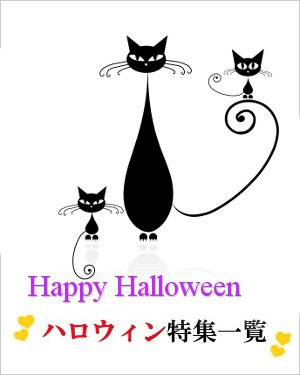ひな祭りの由来は?意味は?ひな祭り(桃の節句)の食べ物にも意味があるって本当?

3月3日はひな祭り。「女の子のお祭り」や
「桃の節句」とも呼ばれる 『 ひな祭り 』 ですが、
一体、いつ頃から行われていたのでしょうか?
皆さんは、由来や意味をご存知ですか?
他にも、ひな祭りで食べる行事食にも、
食べ物ひとつひとつに、深い意味があります。
由来や意味を知ることで、よりひな祭りを楽しめるはず。
ぜひ、桃の節句のひな祭りについて、知識を深めてみませんか。
Contents
ひな祭りの由来は古代中国にあった!?流し雛って何?

ひな祭りの由来はなんと、古代中国の風習から来ていました。
古代中国では季節の変わり目に、邪気を祓うための儀式を行う
風習があったそうです。
その儀式とは、水辺での禊や、水の流れのある庭園などで盃を流し、
自分の元へ流れ着くまでに詩歌を詠む、” 曲水の宴 ” を行った
「 上巳(じょうみ)の祓い 」と呼ばれるものでした。
その上巳の祓いが日本に伝わった際、自分の身代わりとして
植物や紙で作った人形に、穢れを移し、水に流す風習になったそうです。
後に 『 流し雛 』 と呼ばれるこの風習が、ひな祭りの由来となっています。
最初は、女の子とは関係のない風習だったのですね。
ひな祭りが女の子のお祭り(桃の節句)になった理由は?

平安時代は、宮中で行われていた上巳の祓いですが、
室町時代には、3月3日に固定されるようになります。
上巳の祓いが女の子のお祭りになったのは、江戸時代になってから。
その頃に3月3日は「五節句」の一つとなり、年中行事になります。
そして、男の子の祭りである「端午の節句」があるのに対し、
女の子の祭りが存在しなかった事から、
桃の節句とも言われる3月3日の「上巳の節句」を、
女の子の祭りとしたのが、その理由です。
ひな祭りに込められ意味とは?なぜ、ひな人形を飾るようになったの?

女の子のお祭りである 『 ひな祭り 』 には、
という意味が込められています。
そこで、元は人形(ひとがた)であった、ひな人形を飾るようになったとか。
流し雛では、植物や紙であったひな人形も、徐々に
子供の遊び道具や、飾りとしての意味を強め、
最終的には豪華なひな人形へと変化したようです。
ひな祭りには女の子の幸せを願う、
深い意味が込められていたのですね。
行事食の食べ物にもそれぞれ意味があるって本当?

ひな祭りで食べる行事食には、ひとつひとつに意味があります。
意味を知れば行事食をますます、美味しく感じられるかもしれませんね。
『 ひなあられ 』

飴に砂糖をまぶし炒った和菓子、ひなあられ。
ピンク、緑、黄、白は四季を表しています。
その事から「 1年中幸せに過ごせますように 」
という意味込められています。
『 白酒 』

もとは桃の花びらをつけた、「桃花酒」が飲まれていました。
桃には、邪気を祓う力があるとされていた事から、
飲まれるようになりました。
『 菱餅 』

緑、白、ピンクが重なった菱餅。
・緑は「 健康長寿 」
・白は「 雪 」
・ピンクは「 桃 」を表しています。
雪がとけて草が生え、桃の花が咲くという意味が込められています。
また、緑には増血効果のあるヨモギ、白にはケシ実が使われ清浄を表し、
ピンクには解毒作用のあるクチナシが色付けに使われ、
健康を願う意味が込められています。
『 はまぐりのお吸い物 』

はまぐりの殻は対になっており、他の貝とは合わない事から、
良縁に恵まれるという意味が込められています。
『 ちらし寿司 』

ちらし寿しの具に使われるレンコンには「 見通しがきく 」、
エビは「 長生き 」、豆は「 マメに働ける 」という意味があります。
また彩りや春らしい華やかさから、ひな祭りの定番料理になりました。
まとめ
[youtube-adds id=”https://www.youtube.com/watch?v=YORBK20mX74″ player=”3″ style=”mi-flower”]今回はひな祭り(桃の節句)の由来や意味、行事食の
食べ物、ひとつひとつに込められた意味をご紹介しました。
ひな祭りが現在のような形になるまでには、長い歴史がありましたが、
女の子の幸せを願う想いが、脈々と受け継がれているのですね。