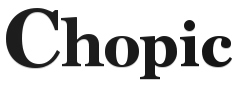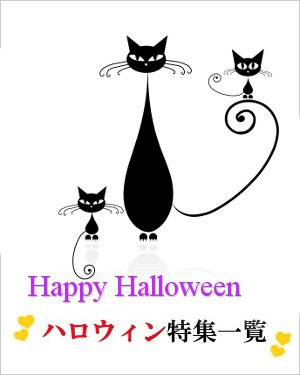五月人形のしまい方(片付け方)4種類の飾り方まとめ!【保存版】|収納箱と収納場所についてもお答えします

端午の節句も終わってしまいました。
五月人形を囲んで、素敵な時間を過ごした方も、
そろそろしまう準備を始める頃ではないでしょうか。
五月人形を正しいしまい方・片付け方( ※以後 ” しまい方 ” )で
収納すれば、長く、美しい状態を保つ事ができますし、
その為に必要な道具も、揃えておきたいものですよね。
でも五月人形って、飾り方にたくさんの種類があるし、
どうやってしまうのが良いのか・・・、また
収納場所はどこが良いか、いまいちよく分からない・・・。
そんな方のため、今回は五月人形のしまい方の手順や、
収納に適した収納場所についてを、詳しくまとめてみました!
まだ片付けが終わってない方は、ぜひ参考にして下さいね。
Contents
五月人形をしまう時に揃えておきたい物は?

五月人形を扱う際には、薄手の手袋をして、
素手で触るのは避けましょう。
人形に直接、手垢や汗が付着すると、変色の原因になりますし、
五月人形の装飾部分の金具が、サビてしまう事もあります。
五月人形についた、ホコリを払うための
毛ばたきは、素材選びが重要です。
五月人形を傷つけないように、柔らかい羽根の
毛ばたきを選べば安心ですね。
( 眼鏡ふきなど )
五月人形についてしまった、汚れをふきとる際は、
清潔な柔らかい布を使いましょう。
ティッシュやタオルの種類では、傷がつく恐れがあるので、
眼鏡ふきなどで、やさしく乾拭きするようにします。
( 天然素材の紙・和紙 )
五月人形を収納する前に、飾りや人形をそれぞれ
天然素材の紙や、和紙で包みます。
その際、強く巻きつけてしまうと
型崩れしたりするので、優しく包んで下さいね。
また紙を優しく丸めて、すき間に詰めれば、緩衝材にもなります。
ちなみに、兜の鍬形など金属部分は、新聞紙で包んでも構いません。
インクがサビを防ぐ役割をしてくれます。
※防虫剤は少量使用で
五月人形を箱に収納する際に、直接人形や
収納箱の金属部に触れないよう、一緒に防虫剤を入れます。
衣類用ではなく、出来れば人形用の防虫剤を使用して下さい。
その時、最初に使用した防虫剤と同じ物を、毎年使うのが重要です。
別の系統の物を使うと、化学反応によって水が出たり、
プラスチックを溶かす事があります。
※少量使用で
昔から使われてきた天然樟脳も、穏やかな効き目で、
五月人形の防虫剤としておすすめです。
天然樟脳を使用する場合、定期的に取り替える
必要があるので、注意して下さいね。
( 必要に応じて少量 )
五月人形は湿気が大敵です。保管場所によって
必要そうなら、防湿剤や乾燥材を使います。
乾燥しすぎも良くないので少量にしておきましょう。
そして重要なポイントですが、複数の薬剤、
防虫剤などと一緒に、混ぜて使用しないでください。
※化学反応が起こる場合があります。
めん棒・脱脂綿・毛先を潰した小筆は、
毛ばたきで落としきれない、ホコリを払うのに便利です。
使用する際は、優しくそっと使うようにして下さいね。
五月人形のしまい方(片づけ方)をご紹介!|兜・鎧・収納飾り・ケース飾り
五月人形のしまい方 ① ・・・ 『 兜飾り(平飾り) 』

飾っている間についたホコリを、
毛ばたきを使って、やさしく払い落とします。
落ちないホコリがあれば、めん棒や小筆を使いましょう。
兜の鍬形、竜頭(おでこ辺りの装飾)などを、
飾り付けた時と逆の順番で外していきます。
特に竜頭は壊れやすいので、注意して扱いましょう。
分解した装飾は、ひとつずつ清潔な柔らかい布で拭き、
紙に包んで傷がつかないように包みます。
兜本体を紙に包んで櫃(ひつ)に収納し、その周囲に
取り外した装飾を入れていきます。
無理に詰めると、変形の原因になるので注意して下さい。
飾りの仕様によっては、兜の下に装飾を
収納する場合もありますので、
最初に入っていた状態に戻します。
弓太刀や飾りなどの、付属品を収納していきます。
それぞれ箱に収納して、傷が付かないようにしましょう。
屏風は内側の絵を保護する為、紙を挟んで畳みます。
絵柄が、盛り上がっていたりする場合は、畳んだ時に
傷が付かないよう、緩衝材を挟んでおくのをおすすめします。
また、台が組み立て式の場合、部品と一緒に収納します。
※塗りの台、特に黒塗りの台は、傷がつきやすく目立つので
特に注意して取り扱いましょう。
各飾り本体と、櫃の金属部に直接触れないよう、
収納箱の隅に防虫剤を少量おけば、片付け終了です。
※防虫剤は櫃の内部には入れず、外部に入れましょう。
※しまい方の手順などが違いますが、動画もぜひご参考下さい。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[youtube-adds id=”https://www.youtube.com/watch?v=04Xo1PtIYoM” player=”3″ style=”mi-wood2″]
五月人形のしまい方 ② ・・・ 『 鎧飾り(平飾り) 』
飾っている間についたホコリを、
毛ばたきを使って、やさしく払い落とします。
落ちないホコリがあれば、めん棒や小筆を使いましょう。
鎧を、飾りつけた時と逆の順番で、全て分解します。
胴体部分は中の芯棒を、外すものと外さないものがあります。
仕様によって異なるので、注意して下さいね。
分解したら装飾部分などを、清潔な柔らかい布で拭き、
それぞれ紙で包み込んでいきます。
最初に、胴体部分を櫃(ひつ)に収納し、
小物を胴体の中や、すき間にソフトに詰めていきます。
兜は逆さにして収納すると、入れやすいですよ。
弓太刀や飾りなどの、付属品を収納していきます。
それぞれ箱に収納して、傷が付かないようにしましょう。
屏風は内側の絵を保護する為、紙を挟んで畳みます。
絵柄が、盛り上がっていたりする場合は、畳んだ時に
傷が付かないよう、緩衝材を挟んでおくのをおすすめします。
また、台が組み立て式の場合、部品と一緒に収納します。
※塗りの台、特に黒塗りの台は、傷がつきやすく
目立つので特に注意して取り扱いましょう。
各飾り本体と、櫃の金属部に直接触れないよう、
収納箱の隅に防虫剤を少量おけば、片付け終了です。
※防虫剤は櫃の内部には入れず、外部に入れましょう。
五月人形のしまい方 ③ ・・・ 『 コンパクト収納飾り 』
飾っている間についたホコリを、
毛ばたきを使って、やさしく払い落とします。
落ちないホコリがあれば、めん棒や小筆を使いましょう。
兜飾りの場合は兜を、鎧飾りの場合は
鎧と兜を分解し、装飾を清潔な柔らかい布で拭きます。
それぞれの飾りを紙で包んで、飾りを入れる
箱があれば、箱の中に収納します。
弓太刀や飾りなどの、付属品を収納していきます。
それぞれ箱に収納して、傷が付かないようにしましょう。
屏風は内側の絵を保護する為、紙を挟んで畳みます。
絵柄が、盛り上がっていたりする場合は、畳んだ時に
傷が付かないよう、緩衝材を挟んでおくのをおすすめします。
防虫剤を入れれば片付け終了です
全てを箱の中に収納したら、
飾り台の収納スペースに入れて保管します。
五月人形に直接触れないよう、箱の隅に
防虫剤を少量おけば、片付け終了です。
五月人形のしまい方 ④ ・・・ 『 ケース飾り 』

画像出典:東京 『 秀光人形工房 』
ケース飾りはお手入れが簡単です。
飾っていた間についた、ホコリや汚れを、
毛ばたきや柔らかい布で払います。
そして、収納箱に入れて保管します。
この時、防虫剤を入れる場合ですが、ケースの中に
直接入れないようにしましょう。
※ケースの外側や、ケースの上部に置きましょう。
収納箱は段ボール?それとも桐の収納箱が良いの?
ここまでは、五月人形のしまい方をご紹介してきましたが、
肝心の収納箱には、何が適しているのでしょうか。
一般的な収納箱として定番の、段ボールと桐の箱を比較して、
メリットやデメリットを知っておきましょう。

まず、比較的手に入りやすく、サイズ展開も意外と豊富、
安価なのもメリットの 『 段ボール 』 ですが、
虫が付きやすく、湿気に弱いというデメリットがあります。
ですので、乾燥剤を使用した方が良い場合があります。
また、空気の入れ替えをする際に、新しいダンボールへの
定期的な交換をした方が、良いケースもあります。
ちなみに、段ボールを使用する際は、数カ所穴を開けて
空気の通り道を作るようにしましょう。

それに対して 『 桐の収納箱 』 は、メリットが多いのが特徴。
虫がつきにくく、吸湿性に優れているので、
収納箱の中を、常に乾いた状態で保つ事ができます。
他にも ” 発火しにくい ” ” 防腐成分を含む ” など
五月人形の収納箱としてぴったりです。
ただ、費用が高いのがデメリットと言えます。
段ボールを使用する場合は、十分に対策する事。
可能なら、桐の収納箱を使った方が良いみたいですね。
五月人形をしまうのに適した 「 収納・保管場所 」 について
五月人形を、来年までしまっておく保管場所ですが、
出来るだけ湿気が少なく、風の通りが良い場所を選びましょう。
直接日光が当たらない場所や、乾燥しすぎないのもポイントです。
具体的には、押入れの上段や天袋など、高い場所がおすすめです。
たまに押入れを開放して、虫干しするようにして下さい。
他にも、高い家具(タンスやクローゼット)の上などに、
布をかぶせて置いても良いですね。

今回は、五月人形のしまい方(片付け方)、
そして収納箱と、保管場所についてご紹介しました。
毎年の事になりますので、しっかりと覚えておけば安心ですね。
来年また綺麗な五月人形で、端午の節句をお祝いするためにも、
片付けるのは大変ですが、頑張りましょうね!
◇ 五月人形のについての基礎知識 関連ページ ◇
>> 五月人形の飾り方の種類について|平飾りや段飾り、収納飾りなど
>> 『 五月人形は誰が買う 』 について|関西と関東での違い、他
>> 『五月人形を飾る時期としまう時期』 について|初節句の時と 二年目以降の時期についても
◇ 五月人形選び 関連ナビページ ◇ ※現在作成中